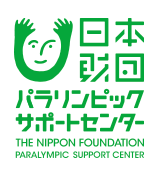2016年8月25日
リオパラ直前! ライター座談会その2〜最も印象的だったパラリンピック
長年にわたりパラスポーツを追いかけ、その魅力を知るライター3人が、パラリンピックの魅力や見どころを語るライター座談会。第2回の今回は、印象的だったあのパラリンピック開催都市について語ります。
最も印象的だったパラリンピック開催都市

―みなさん、これまで国内外で行われる世界的な大会を多数、取材されており、その中にパラリンピックもあるわけですが、一番印象に残っているパラリンピックの開催都市を教えてください。
荒木 ロンドン!
瀬長 ロンドン!
星野 ロンドン!
―3人ともロンドンですか。
星野 ロンドンは、どの会場もほぼ満員で、盛り上がり方がすごかったんですよ。
ロンドン郊外にあるストークマンデビルは、パラリンピックの発祥の地なので、パラスポーツも浸透しているからかなと思っていたのですが、実はロンドンがオリンピック・パラリンピック開催権を取った05年当時は、ロンドンっ子はパラのことをさほど知らなかったんですってね。
荒木 そうそう、「Meet The Superhumans」というかっこいいテレビCMが流されるまでは、さほどパラに興味がなかったというデータがあるんですよ。開催日が近づくにつれてさまざまな情報が入るようになり、足を運んでみたらすごくおもしろいとわかったため、どんどんお客さんも増えていったということのようです。
瀬長 その背景として、イギリスにはそもそもスポーツが文化として根付いていることも大きいんじゃないかと。サッカーやテニス、ゴルフなどの発祥の地ですし、大きな国際大会も開かれているので、スポーツを観る目が養われているんですね。だからこそ、パラスポーツのおもしろさにも気づけたんでしょう。
荒木 応援を聞いていても、足がないから、義足を付けているから感動するというレベルではなく、スポーツとして「すごいぞ」という興奮の渦が会場内に充満していて、スポーツの一分野として楽しんでいると感じました。そこにいるだけで感動するぐらいの熱の入った応援が繰り広げられていましたからね。
瀬長 客席のスタンディングオベーションがすごかった!
荒木 それに、一般的には、自国の選手が出ている試合は満員になるけど、その試合が終わると、お客さんが帰ってしまい、がらんとしてしまうものです。もちろん、ロンドンでも、イギリス人の出番が終わると観客が減ってはいましたが、それでもほぼ満員状態でした。自国も応援するけど、競技としておもしろいからほかの国の選手も応援するし、いい試合は観たいということなんでしょう。これは今までに見たことがない光景でした。本当にすごいことですよ。
瀬長 しかも、表彰式までちゃんと帰らずに待っている。これは、日本ではいまでも見られませんよね。
私はスポーツを楽しむ態度もいいなと思いました。日本では、まだまだお行儀よく観なくてはいけませんみたいな雰囲気がある気がしますけど、ロンドンパラの会場では、お客さんたちがビールとフィッシュアンドチップス片手に観戦してたのがうらやましかったです。
星野 たしかに、どの会場でもMCが盛り上げてましたし、ハーフタイムショーがあったり、観客がウエーブをしたりと、エンターテインメントとして楽しんでいましたよね。
ゴールボールのように、シーンとして観戦なければいけないような競技でさえ、タイミングを見計らって音楽が流されていましたし、ハーフタイムでは踊り出すような観客もいたんです。その姿が大リーグやNBAのように会場に設置された大画面に映し出されて、またさらに盛り上がったりしてね。
ボランティアも含めた国民全部がチームの一員

瀬長 私は、ボランティアの存在は大きかったなって思ってます。「エクセル」というパワーリフティングや柔道の会場近くのホテルに泊まっていたのですが、徹夜で原稿と格闘していると、締め切り時間の朝7時ぐらいに、ボランティアが陽気に歌い始めるのが聞こえてくるんです。その歌声を聴いて、「朝が来たんだな」って思いましたし、その歌声に元気をもらってましたね。
私は英語ができないのですが、それでもボランティアは根気強く接してくれましたし、気持ちよく過ごすことができました。会場案内もわかりやすくて、ストレスなく取材できたのは、ボランティアのおかげです。
星野 明るさや親切さに無理がなくて、ボランティア文化が根付いているなと感じさせられましたよね。
私自身、盲人ランナーの伴走ボランティアをきっかけに、パラスポーツの取材を始めたこともあり、いろいろな大会のボランティアを取材しています。ロンドンでは、イギリス全体で大会を盛り上げようと、国民はもちろん、留学生などイギリスに在住している人たちの中からボランティアを募集し、そのボランティアを「ゲームズメーカー」(大会を作る人)と呼んでいました。また、「チームGB」(Great Britain)といって、選手もボランティアも含めた国民全部がチームの一員だと意識づけしたんです。そのおかげでしょう、ボランティアから「自分たちは大会を作る一員なんだ」というプライドを感じましたね。また、パラ発祥の地で行われるパラリンピックだという誇りがあるからこそ、成功させなくてはという気概も感じました。
荒木 チームGBとしての一体感を演出するクライマックスは、閉会後のパレードでしたよね。
星野 そう! パラの閉会式の次の日に行われたのですが、オリンピックとパラリンピックの選手、そして、ボランティアの代表も一緒にパレードをしたんです。しかも、バレーボール車にはバレーボールとシッティングバレーの選手というように、オリンピックとパラリンピックの区別なく、しかもメダルの有無にかかわらず、同じ競技を戦った選手全員が一緒に同じ車に乗っていたのが印象的でした。
瀬長 日本ではまだパラが始まってもいないのに、オリンピックだけ、しかもメダリストだけで銀座でパレードをしちゃってましたもんね。この違いにはあ然とさせられますよね。
星野 ロンドンは、街全体の雰囲気も良かったですよね。実は街自体はバリアフリーではなく、バリアアリー(有り)なんです。地下鉄も古いし、階段もいっぱいあるし。だけど、選手たちはぜんぜんバリアを感じなかったんですって。というのは、地下鉄の入り口でまごまごしていると、何も言わずに車いすを抱えて移動させてくれて、お礼を言う間もなく、「グッドラック」って言って行っちゃうそうなんです。そういう行為が根付いているんですよ。
選手から、「そんなこと日本ではできないよね、星野さん」って言われたんですけど、「いやあ、すみません」って言うしかなくって。
ロンドン大会から見えてくる東京大会の課題
瀬長 そういうことを考えると、日本にとって、パラリンピック開催はかなりハードルが高いんじゃないかって心配になっちゃいますよね。
星野 「TOKYO」って、オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まった日は、私たちはそれぞれ山口で国内最高峰の陸上競技の大会の取材中だったんです。そこで、選手に「決まりましたね、東京」って言ったら、みんな結構テンションが低くて、「いやあ、ロンドンみたいに盛り上げられるかな」って口々に言ってたんですよ。
瀬長 あの時、会場がガラガラだったんですよね。
星野 ロンドンからちょうど一年後の9月の大会だったので、あの盛り上がりを知っている人にとっては、つらいですよね。
瀬長 ある若手選手が「ぼくもロンドンのように、たくさん観客がいるパラリンピックでプレーしたかったのに、日本に決まっちゃって残念。モチベーション下がるな」って言ってましたよ(苦笑)。
星野 若手はロンドンのことを先輩たちに聞いているし、ロンドンに行った人たちはその熱気を肌で感じていますから、そう思うのも当然なんです。
とはいえ、さすがに選手に「東京で残念」って言われたのはショックでしたし、これはいかんと思いました。だからこそ、私たちが会場を満員にするぞというぐらいの意気込みでがんばってます。
瀬長 行動を起こす記事を発信していきたいですよね。
<第3回は、ライター陣が独断と偏見で語るリオパラリンピックの見どころを語ります! お楽しみに>
出席者
荒木美晴
MA SPORTS代表、ライター。滋賀県大津市在住。1998年長野パラリンピックでパラスポーツと出合い、その魅力に開眼。この感動や興奮を多くの人に伝えたいと、大阪の衣料問屋のOLからライターに転身。以後、世界選手権やパラリンピックをはじめ、国内外の大会を精力的に取材。記事は、障がい者スポーツ専門サイトなどで発信している。初パラリンピック取材は、00年シドニー大会。
瀬長あすか
フリーランスエディター&ライター。東京都江東区出身。日本財団パラリンピックサポートセンターWEBエディター。学生時代より記者活動をスタートし、ブラインドサッカーとの出合いをきっかけに、パラスポーツを追いかけ始める。2011年よりフリーに。現場主義をモットーとし、取材したパラスポーツは50以上。初パラリンピック取材は、04年アテネ大会。
星野恭子
フリーランスライター。新潟県出身、東京都在住。偶然の出会いから始めた盲人マラソンの伴走ボランティアで、障がい者の能力の素晴らしさを知るとともに、パラスポーツの魅力に目覚め、メインテーマのひとつとして追いかけ始める。アスリートだけでなく、周囲で支えている人たちにを当てた記事も好評。著書に『いっしょに走ろっ!』(大日本図書)など。初パラリンピック取材は、08年北京大会。
text by Masae Iwata , photo by X-1