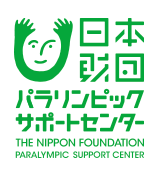2016年9月13日
リオパラリンピック陸上競技日本チーム主将の松永仁志。後輩たちとともに走る。

リオパラリンピック日本代表の中で選手数が最も多いのは全36選手を擁する陸上競技陣。その主将を努めるのが松永仁志(43歳)だ。「出場3度目だし、年もいってるからね」と謙遜するが、実は面倒見のよさで知られる兄貴分。18歳から68歳までの多彩な顔ぶれのまとめ役として見込まれた。
所属する「WORLD-AC(ワールドアスリートクラブ)」は今年3月に岡山市で発足した車いす陸上の実業団チームだ。障がい者スポーツの実業団は全国的にみてもまだほとんど例がないが、松永はチーム誕生に奔走し、選手兼監督として活躍する。
クラブは松永が2014年から勤務する人材派遣関連会社「グロップサンセリテ」に車いす陸上部として設立され、クラブ名の「WORLD-AC」には“岡山から世界へ”の思いが込められている。現在は松永のほか、2015年世界選手権の金メダル獲得でリオパラリンピックの代表権を得た佐藤友祈と、2009年アジアユースパラ競技大会の金メダリストであるスプリンターの生馬知希が所属する。このクラブ設立も、松永の経験と面倒見のよさがきっかけになっている。
がむしゃらに取り組んできた30代
松永は中学、高校と陸上部に所属していたが、高校2年時にバイク事故を起こし、車いす生活になる。リハビリを経て社会復帰を果たし、設計会社に勤務中だった2000年、シドニーパラリンピックの映像を目にする。自分と同じ車いすユーザーが競技用車いすでトラックを躍動する姿や、その競技性の高さに衝撃を受けた。「こんな舞台があるなら、出てみたい」
本格的に陸上を始めると、目標を次の2004年アテネパラリンピックに定め、がむしゃらに取り組む。金曜夜に仕事を終えると、岡山から練習仲間のいる大分市まで車を飛ばし、週末2日間みっちり練習。月曜未明に岡山に戻ると、そのまま出勤という日々を過ごした。自分なりにお金も時間もかけたつもりだったが、それでも参加標準記録を突破できず、代表入りを逃した。
「同じことをやっても同じ結果にしかならない。1年間だけ競技に没頭しよう。それで成長しなければ、諦める」。そう腹をくくり、10年勤めた会社を辞めた。“プロ転向”といえば聞こえはいいが、実際は無職。アパートを引き払い、親に頭を下げて実家に戻り、貯金もつぎ込んだ。
背水の陣が功を奏す。競技に専念したことで、練習時間の増加と同時に、休養時間も増えた。おかげで、充実のトレーニングと十分なリカバリーという好サイクルが確立でき、アスリートとして順調に成長。欧州選手権で金メダル獲得など国際大会でも実績が出始める。2007年には無事に参加標準記録を突破して、念願だった2008年北京パラリンピックに初出場を果たす。結果は2種目(400、800m)とも予選敗退で悔しい思いもしたが、すべてをかけて挑戦したかいのある、素晴らしい舞台だった。
「もう一度」の思いで現役続行。北京で「パラリンピアン」となったことで少しずつスポンサーもついたが、生活できるほどの収入にはならず、非常勤の仕事も行いながらの競技生活だった。それでも、積み重ねた練習ノウハウをベースに身体も気持ちも鍛え上げ、2012年ロンドンパラリンピックにも連続出場。出場した3種目(100、200、800m)とも惜しくも決勝には進めなかった。
悔しい思いを胸に3度目のリオを目指す練習過程で、故郷を離れ、岡山市内の職業訓練校で学んでいた佐藤と生馬と出会う。自身の練習のかたわら、二人の練習にもアドバイスを送るうちに、二人のアスリートとしての才能に気づき、社長に直談判し、昨秋、二人をあいついで自社に入社させた。さらに、社内クラブまで設立したのは、伸び盛りの若い二人に少しでも充実した練習環境を提供したいという思いからだ。そのベースには北京、ロンドンへの道中で、「練習環境を整えれば、結果は出る。ただし、職業など生活の基盤が不可欠。きちんとした枠組みが必要だ……」という、松永自身が実感した思いがある。
実際、二人とも松永と練習を始めて以降、めきめきと実力をつけている。生馬は日々成長が見え、来春には国際戦デビューを予定している。リオ切符を射止めた佐藤は、「この半年でビックリするほど成長できたのは監督のおかげ。リオに一緒に行けるのも心強いし、嬉しい」と話していた。
日々の練習で、佐藤や生馬の競技に取り組む純粋な姿勢に、松永自身も競技をはじめた頃のがむしゃらだった自分を重ね、初心に還ることができるという。
こだわり続けた400mで世界の強豪たちに真っ向勝負

そうして迎えたリオパラリンピックで、松永は2種目にエントリー。特にこだわってきたのが、400mだ。終始セパレートコースでレースが進むのでかけ引きがなく、地力がないと勝てない。真の力勝負に心惹かれたのだ。4年間ストイックに競技に取り組み、“史上最強の自分”という手応えとともに、リオの地で世界の強豪たちに真っ向勝負を挑んだが、残念ながらまたも決勝進出はならなかった。「走った感触は悪くなかったが、力不足。それに尽きる結果」と悔しさをにじませつつ、たどってきた道のりには納得の表情を見せた。
松永は、諦めず、食らいつく走りで、日本チームにも力を与えるつもりだ。
text by Kyoko Hoshino/NO BORDER, photo by X-1,Asuka Senaga