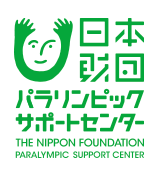2016年9月17日
水泳のエース木村敬一、4日連続のメダルで意地
僅差の悔しい銀メダル

「負けて悔いが残らないことはない。ずっと死ぬまでモヤモヤするんだろうな」
リオパラリンピック7日目の水泳男子100mバタフライS11(視覚障がい)決勝レース。昨年の世界選手権で優勝し、世界ランキング1位で迎えた木村敬一はわずか0.19秒差で金メダルをつかみ損ねた。50mをトップで折り返し、後半は頭ひとつリードしたときもあったが、残り10mほどでスペイン選手に抜かれ、2着でのゴール。
視覚障がい選手は自分の位置やライバルとの距離を、見て把握することが難しく、蛇行もしやすい。この日の木村もゴール前80mほどで、隣のレーンの選手と腕がぶつかりあったことで、「接戦状況」を把握したという。
冒頭の言葉は、悔しい敗戦直後に木村が紡ぎだした一文だ。先天性視覚障がいのため、幼いころから映像でなく、言葉の世界に住む木村は心に響くフレーズを生み出す天才で、いつも明るく、軽妙なコメントで報道陣を時に笑わせ、時に煙に巻く。だがこの日は、そんな木村の姿はなかった。「今の本音」がおそらく口から飛び出したのだろう。
過去2大会のパラリンピックで獲得したメダルは銀と銅の2つ。3度目のリオには金メダルを獲りにきた。大会5日目に初レースを迎えた木村は、50m自由形で幸先よく銀メダルを獲得する。本命種目ではなかったが、トップと0.95秒差の銀。悲願の金メダルに向け、よい弾みになったと思われた。
だが、2レース目の100m平泳ぎは昨年の世界選手権でも優勝し、金メダルが期待されたが、結果は先頭に2.8秒も離されての3位で銅メダルに終わる。自己記録にも及ばず、レース後は「きつかった」と何度も繰り返した。
ちょうど2ヵ月前、横浜市で開かれた「ジャパンパラ水泳競技大会」で、木村はリオ前最後の公式戦に臨んだが、100m平泳ぎではスタートで足を滑らせ入水したことで方向感覚が狂ったことをきっかけに、結局2レーン分もコースアウトして失格になった。これほど大きなコースアウトは、「4年ぶりくらいかな」と振り返り、報道陣を心配させた。だが、4年前にも同様に、ロンドン大会直前のジャパンパラ大会で破れた水着で泳いでいた恥ずかしいエピソードを披露し、大舞台前のミスは恒例だとでもいうように、「厄落としっす」とうそぶいた。
そのジャパンパラでは100mバタフライも精彩を欠いたが、その要因のひとつとして、「水を飲んだ」と明かした。「2リットルくらい……、嘘です。今は不安ですが、(不安な気持ちは)2ヵ月後には忘れるでしょう」と、取材に対して答えながら、まるで自らに言い聞かせるような、そんな言葉を紡いでいた。
そういえば、2013年からタッグを組む、日大の野口智博教授は木村のコメント力の高さについて、「彼は、障がい者に夢を与える存在だと思うし、一般の人が見ても、『こいつはスゴイ!』と評価されるような存在になるべき人。だから、暗い感じでなく、周囲を楽しませる存在でいたほうがいいと思うので」と評価している。
軽妙なコメントも復活

さて、リオの3本目のレースは大本命の100mバタフライだった。この日のために、この4年間肉体改造にも取り組んできた。筋肉量を増やして、体に取り込める酸素量を増やし、持久力を高める目的がある。痩せやすい体質の木村にとって、食べて鍛えるトレーニングは過酷だったが、以前とは見違えるほどたくましくなった。さらに、昨年、世界王者になって以降は、「悲願の金メダル」への期待が周囲はもちろん、木村本人のなかでも急速に高まっていた。
満を持して臨んだレースは、僅差で敗れ、銀メダル。「悔しい」「苦しかった」「実力がなかったのかな」……。レース後に絞りだされたのは“ひねり”のない言葉ばかり。最も自信をもって臨んだバタフライで金メダルを逃したショックは計り知れない。
一夜明け、失意の木村は再びスタート台に戻ってきた。エントリー5種目中、最も厳しいと思われた種目、100m自由形だったが、59秒63をマークして3着。きっちり銅メダルを手にした。重圧と緊張感が日増しに高まるなか、4日連続のメダル獲得だ。気持ちをどう、切り替えたのだろう。
世界記録を更新した先頭からは3秒以上離されたとはいえ、59秒台をマークした力泳は今後につながる希望のレースになったのではなかろうか。
実はこの試合、運営上の都合で進行が中断し、木村は予定されたスタート時刻から40分も待たされた。このときの心境を聞かれると、「これで俺は回復できるぜ」と答えた木村。明るく、前向きな言葉を紡ぎ出す、本来の姿がそこにあった。
5つ目のレースは、200m個人メドレー。5日連続のメダルとはならなかったが、疲労の中で戦い抜き、2分28秒76をマークし、4位だった。
試合後、報道陣に「4年後、東京パラリンピックに挑戦するか」と質問され、「明日の自分に聞いてみようと思います」と、木村は応えた。
まだまだ、いける。大丈夫――そう思わせてくれる、「木村節」の復活だった。
text by Kyoko Hoshino/NO BORDER, photo by X-1