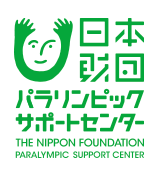2016年11月22日
陸上競技400m銅メダルの辻沙絵。「会場に足を運んで、パラスポーツの面白さを感じて!」

リオパラリンピック以降、メデイアやイベントなどでパラリンピアンの登場が増えている。そのひとりが辻沙絵だ。彼女は陸上競技を始めてわずか1年半でリオ大会に初出場し、100m、200mでは入賞し、400m(以上T47クラス)では銅メダルを獲得するという快挙を成し遂げた辻。一躍、帰国後は、「パラスポーツの顔」として、その魅力を伝えて回る、忙しい日々を過ごすことになったのだ。
リオ大会は多くの観客による、楽しく熱狂的な応援風景が話題となった。リオでの最終レースとなった200m決勝後に辻は、そんな大舞台を振り返り、「パラリンピックは素晴らしい大会でした。国内ではこんな雰囲気の大会はなく、すごく興奮しました。(2020年)東京大会でもこんなふうに観客に観てもらい、パラスポーツは楽しいと思ってもらいたい。できれば、『この選手を見たいから』と会場まで足を運ぶ。そんな風になってほしい」
大観衆の前でパフォーマンスすることの素晴らしさを体験したからこその心からの思いだ。「でも、それにはちゃんと結果を出すことが必要。リオで今の自分のレベルが分かったので、しっかり練習して、もっと強くなりたい」と、アスリートとしての固い決意も心に秘める。
「なんで私がパラリンピック?」だった、約2年前

辻は1994年、右腕の肘から先がない状態で生まれたが、特に自らを障がい者と意識することなく育った。出身の北海道函館市周辺ではハンドボールが盛んだったので、小学校5年のとき、自然な流れで友だちと一緒に学校のクラブチームに入った。腕を使う球技だったが、「小学校の頃はお遊びのようで、みんなと楽しくやれればいいという感じ」で、特に不都合はなかったという。
持ち前の運動神経ですぐに頭角を現した辻は、中学では全国大会に出場し、高校は北海道を離れ、ハンドボールの強豪校、茨城県の水海道第二高校に進学。主力としてインターハイにも出場すると、スポーツ推薦で日本体育大学に入学。ハンドボール部に入り、さらなる高みを目指して練習に励む毎日を過ごしていた。
転機は20年東京大会の開催が決まり、パラリンピック成功に向けて社会的な機運が高まりつつあった、15年の春。腕に障がいのある辻に対し、ハンドボール部の監督から、「パラリンピックを目指してみないか」と勧められた。運動能力テストでスプリント力が特に高く、陸上短距離走の適性が見られたからだ。
だが、10年以上も大好きなハンドボールで健常者と肩を並べ、高いレベルで活躍してきて、最初は「なんで私が、パラリンピック?」と戸惑いが大きかったという。当時の辻はパラリンピックという存在は知っていたが、リハビリの延長で選手と関係者だけの小じんまりとした大会といったイメージしか持っていなかったのだ。
それでも、「(障がいのある)自分にしかできない挑戦」ということで、最初はハンドボールと掛け持ちで始めることにした。すると、短期間で日本記録を樹立するなど急成長。半年後には世界選手権の代表になり、初の国際舞台では100mで6位入賞の快挙を果たす。「ちゃんと取り組んだら、メダルも狙えるかもしれない」。負けず嫌いの心に火がつき、辻はハンドボール部を辞めた。
その後、陸上と真正面から向き合い、スプリンターとして順調に実力を伸ばした辻は、参加標準記録も突破して初のパラリンピック代表の座も手にし、リオの舞台に立った。そこでの活躍は冒頭に記した通りだ。短距離3種目のなかでも最もメダルに近いと思われた400mを重点的に強化し、「絶対にメダルを獲る」と公言して自らを追い込んだ。
そうして迎えたリオの400m。予選は、「確実に決勝に残れるように」と他選手の様子を見ながらラスト100mは流し、1分1秒85の第1組目2着で余裕をもって通過した。翌日の決勝では逆に、前を行く選手には目もくれず、スタートから自分の設定ペースを冷静に守り、最後の直線手前で2人を抜き去り3位に浮上。そのまま粘って1分00秒62でゴールに飛び込んだ。有言実行のメダル獲得にも、前夜は「緊張で眠れなかった」と言い、「いろいろなことを犠牲にしてがんばってきたから、メダルが獲れて本当に嬉しい」とレース後、報道陣を前に涙も流した。
とはいえ、陸上への転向を、「まだ100%良かったとは言えない」という。「そう思える結果を出していないので。(4年後の)東京で、100m、200mでメダル争いをし、400mでもっといい色のメダルを獲って結果が出たら、そのときに初めて100%良かったと言えると思います」と話す。
現在、大学4年生の辻には幼い頃から、「教師になる」という夢がある。だが、卒業してもしばらくは、その夢はおあずけと決めている。「夢中になったら、とことん」という性格なので、少なくとも20年までの4年間は競技に専念する。もう一つの夢、「金メダルを獲る」ことだけを追いかけたいからだ。

text by Kyoko Hoshino, photo by X-1